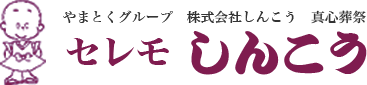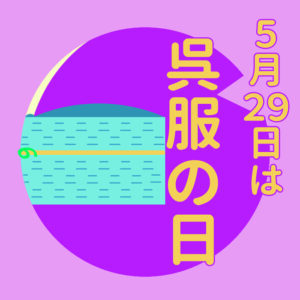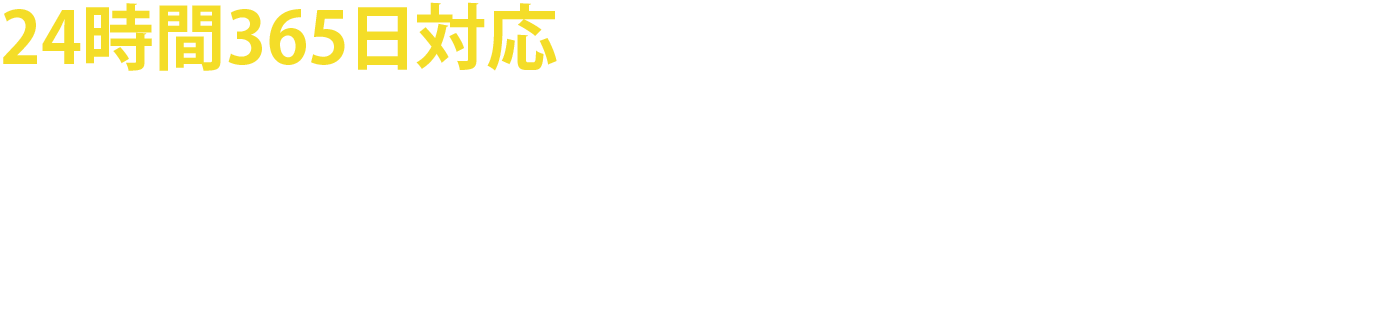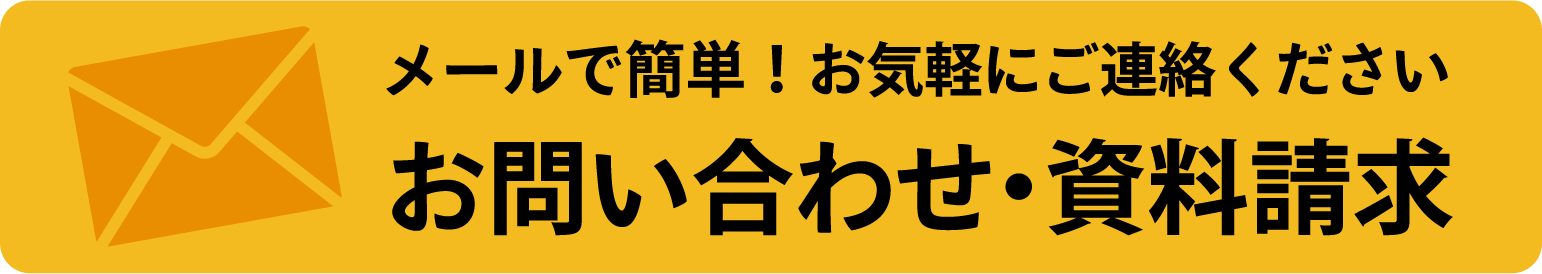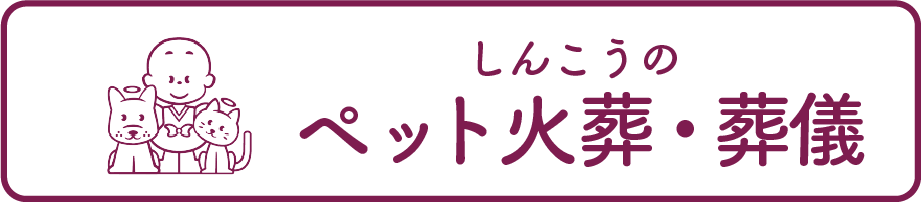家族葬の歴史と現代のトレンド

1. 家族葬の歴史
家族葬の起源は、古くからある日本の葬儀文化の中にあります。伝統的な葬儀では、親戚や友人、地域の人々が集まって大規模に行われることが一般的でした。しかし、近年では葬儀の形が変化し、特に1980年代後半から1990年代にかけて「家族葬」が注目され始めました。
その背景には、核家族化の進行や、都市化に伴う社会の変化、また葬儀にかかる費用や負担を軽減したいというニーズの高まりがありました。
家族葬は、故人の近親者のみで静かに行う小規模な葬儀のスタイルで、一般的には親族や親しい友人のみが参列し、近年では会葬者を極力抑えた形態が増えています。これにより、形式的な儀式や社会的なプレッシャーから解放され、より個人の意向に合わせた葬儀を行うことが可能になりました。
2. 現代のトレンド
現代では、家族葬がますます一般的になり、いくつかのトレンドが見られます。
- 個人化と自由度の増加
家族葬の最大の特徴は、個人の希望を反映させた葬儀ができることです。宗教儀式に縛られることなく、故人や家族の信念、価値観に基づいたスタイルを選べるようになっています。例えば、音楽や写真を多く取り入れたメモリアルセレモニーや、故人が生前に好きだったものを飾るなど、個性を表現する方法が増えました。 - エコ葬やグリーン葬儀
環境への配慮が高まる中で、エコ葬やグリーン葬儀といった選択肢も増えています。例えば、生分解性の棺を使用したり、自然に優しい方法で遺灰を散骨するなど、環境負荷を軽減した葬儀が注目されています。 - 少人数でもアットホームな雰囲気
家族葬は小規模なため、より温かみのある雰囲気で葬儀を行える点が特徴です。故人と親しい関係にある人々が集まり、静かに、そして心を込めて別れを告げることができます。
3. 家族葬の今後の展望
今後も家族葬は、ますます多様化していくと考えられます。葬儀の形式が個人の価値観や希望に基づいて柔軟に変化していく中で、よりパーソナライズされた葬儀が一般的になるでしょう。また、社会的な変化に合わせて、葬儀後のアフターケアや心理的サポートを提供するサービスも増えていく可能性があります。
家族葬は、故人の最後の瞬間を静かに、そして意味のある形で過ごしたいと考える人々にとって、今後も重要な選択肢であり続けるでしょう。